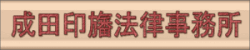瑞牆山
96年の梅雨の頃に書いた原稿です。
さっきから振り払っても振り払っても Doppel ganger が耳について離れない。
梅雨の雲の間から空の碧さがぽっかり空いたばかりというのに
まったく大昔に覚えた暗い悩ましい曲がついてまわる。
少し前に写譜までした「霧と話した」よりは、よほどましかと思いつつそのままにしていたら、危うく Du Doppel ganger と口に上りそうになって急に気がついてやめた。
前の友人の背中がいぶかしげに傾いたがそのまま沢の最後の急斜面を這いあがっていく。石南花に埋まってみたいと奥山の人の気のない山へあるかなきかの踏み趾を辿ってしゃにむにここまで来たがどうも花のイメージが違うようだ。
踏み荒らされた山頂を迂回して行こうと地図にも載らない苔の厚く積もった踏み趾に入り込んで惑ったようだ。こういう惑いも心にぴったりくる。
途中、小さな沢の中程にトタンで囲われた廃屋を見た。
空き缶や空き瓶が無残に散らかっている。
水晶採りの狼藉の趾とは後で山小屋の主人に聞いた。
沢を幾度か最後までつめたが名前も分からぬ支尾根の稜線には裏白(吾妻石南花)の小潅木が立ち塞がりどうにも入り込む余地がない。
ひとりなら蕾のうちの濃い桃色から白に近くなる開花にいつまでもみとれていてもよいが,無理矢理、桃色の花木どもに狼藉を試みるが、見事に細い二の腕に絡み付かれて満足に進めない。入りこんだ箇所さえ不明になってきた。なんとか細腕から逃れて沢の上部に帰りつくと、見上げる雲のちぎれから碧い空が見える。
岩の上の苔のついた状態からみても、どうも人が入らない沢のようだという予感があった。どうも最初からついていない。土曜日なのに宿泊客は我々だけという木賃宿のような宿の車で行けるところまでとの約束で送ってもらうと、純朴な運転手はどうみても車が行けそうもない道をむりやり登ったあげく、沢の対岸を示して道はあの崖を登ったところにあるはずだという。
途中まで這いあがり沢に転落しそうな崖を落ちる落ちると言いながら散々試して3度目にようやく成功したら小1時間は経っていた
そして,山頂へ登りつくとそこはとびきり俗世だった。
帰宅して普段聞かないグールドのブラームスを聞いて不覚にも涙を流しそうになった。