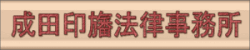24才ころの山旅のことを1990年中にあるサイトに書き込んだものを up しました。古い原稿をなるべく手を加えないまま載せることにしました。
ある山たび
だいぶ昔の話しではあるが、著名な岳に登った。
10月の下旬頃のことで、夏は人の背中を見て登るようなところであるが、この時期は人と出会うこともあまりない。
カールの下方の客もいない小屋に一泊して、翌日は遅く起きて、だたなんともなく登り始めた。下方の著名な観光地(昔は神が住むといわれた)から正面に見えるカールを登っていく径であるが、革靴がやけに重い。
天気が良すぎて、空が暗くみえるという日だったが、誰もいない径をひとり登り始めた。かなりな斜面を登っていく途中で腹具合が怪しくなり、大雉射ち(その意は重大事に及んでいる姿勢の類似性からきている。)に及んだが、なにせ急斜面であり、たぶん観光地から望遠鏡ででもみられれば隠しようもないところだった。
が、終了後、宿主をはなれた物体は、重力が摩擦力に打ち勝ってころころ崖を落ちてゆき、他方、吹きあがってきた風に紙は蒼穹目指して駆け上がっていった。
その一週間前に最終合格の発表を見たばかりの著しく体力を消耗している時分で、感覚も、知覚も鈍く旧式のキスリングの脇ポケットを岩角に引っ掛けて危うく滑落しかかって情けなくも腰を抜かしかかったところもあり、また、岩ばかりのピークとピークの踏み跡を誤って、浮き石だらけの崖を無理矢理下るはめになった。そこは全体が岩や石だけが積み重なってできたピークで、一歩踏む毎に足元からはるか内部までカタンカタンと岩と岩のぶつかる音が伝わっていき、これにはまったく肝を冷やした。
なんとか頂きに辿き、はるか向こうに槍の穂先を望んだが、かってそこを登った時のような高揚感がまったくない。空は青く澄み渡るが、暗く感ずるばかりで、なんともやり切れない喪失感ばかりが湧いてきてどうしょうもない。
なんのために登ったのか、当初の嗤ふべきロマンチックな目的を失い、哀れむべき自己嫌悪と自己憐憫のために登ることだけが目的となりはてていた己に登頂の喜びなどあるはずもない。空しさばかりが風に吹き流されていくばかりだった。
さすがに、頂上直下の小屋付近には登山客が数名がいたが、ここでもまた埃くさいカールへのコースを間違えて危うく岩登りをするところだった。
ある小説で有名な岩崖を覗く気も起こらないまま、そのままカールを下り始める。Z状になった急下りも体力のない状態では苦しい。ときどき見上げると岩屑だらけの頂に下弦の月がかかかっているのが、こちらの気分を映しているようでしばらく見とれていた。
下りきった辺りで日も暮れかかり、カール底の小屋にでも泊まろうかとも思ったが、違和感を覚えた楽しげな人声もあって、そのまま先をいくことにした。途中、そろそろ暗くなってきたので明かりを灯そうとヘッドライトを点ければ薄暗く、電池切れのようだ。憔悴している時に用意をするとこうなるという見本のようだ。遂に、まったくランプの光が見えなくなってしまった。ライターを灯しても風が少しあって光源の用をなさない。そのうち川にでたが、渡り口が分からない。こんなところで不時露営というのは馬鹿げていると流石に少しあせりがくる。ようやく木橋を見つけて渡り、森の中の小道を木々の間からもれてくる月明かりを頼りにこけつまろびつ夜半に横尾の小屋にたどりついた。朝から歩行は15時間ばかりに及び、小屋番からは文句を言われた。
翌朝は、猛烈に痛む右足をひきずり、悄然と観光地に向かう。
高い頂きを目指す山旅は、私の中では遂に終わったようだった。